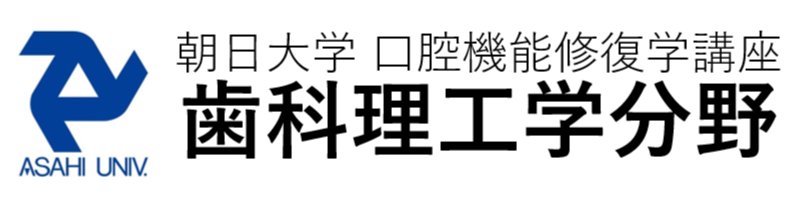分野紹介
臨床と基礎をつなぐ歯科理工学
~歯科理工学で学ぶ、考える、進化する~
歯科理工学分野 澤田智史
歯科理工学では歯科医療で用いる材料や器械・器具と治療技術の密接な関連性を把握するために基礎および応用科学を学びます。歯科材料の多くは口腔内で一時的または長期的に用いられることからバイオマテリアル(生体材料)でもあります。こうした歯科材料や器械・器具は日々、研究・開発・改良がされており、また新たなものが市場に登場しています。我々、歯科医療従事者や歯科医師を目指す学生は社会的背景を理解して、その変化に対応するために知識や技術の向上を目指し、自己研鑽が必要であります。近年では歯科医療のデジタル化が加速し、新たな加工技術(コンピュータ支援設計・コンピュータ支援製造:CAD/CAM)の進歩・発展が著しくあります。その中で、切削加工技術(Subtractive manufacturing)や付加製造技術(Additive manufacturing)によりこれまで使用できなかった材料の使用や従来の方法よりも精度の高い歯冠修復物や補綴装置等の製作が可能となっております。また、AI技術の発展に伴い、歯科医療でもデジタルワークフローの導入によりパラダイムシフトを迎えております。このような背景から現在の歯科理工学ではアナログとデジタルの融合を図った教育と研究の実践が求められております。
[教育面]
歯科理工学は基礎系科目の中でより臨床に近い科目の位置付けにあります。その中で歯科理工学は臨床的な講義内容も多く、臨床現場を経験していない学生諸子が生物や化学等の基礎科学から基礎系科目を学ぶことの大切さを理解することは容易ではありません。そこで、低学年での講義や実習では学生の視点に立ち、歯科理工学の重要なポイントを①材料名、②その材料の組成、③その材料の臨床での使用方法・手順に分け、学生が理解しやすい・わかりやすい教育の実践を心がけて、臨床系科目へと結びつけるシームレスな移行を心掛けております。また、高学年の講義では臨床実習を終えた後に改めて低学年の基礎系科目の重要性を理解していることから、低学年で教授した内容の復習と臨床実習で得た知見を融合する形でアップデートしていきます。これからの歯学教育の中で歯科理工学教育の教授内容の位置づけから、2点の充実を図る必要があります。1点目は新しい歯科材料や技術の導入に対応できる能力を教授します。近年、CAD/CAM技術については保険収載される項目が増えてきており、歯科医師国家試験出題基準にも明記されております。2点目は令和4年度モデルコアカリキュラム改訂による歯科医療機器への教授内容を検討します。臨床現場で使用する方法もさることながら、基礎から臨床への移行がシームレスになるように教授内容を検討し、基礎と臨床で繰り返し教授することで知識の定着を図りたいと思います。そのためにも、科目間での連携の充実を図り、基礎と臨床の融合を推進することが必要不可欠であると考えております。
当分野の学生生活への対応は、学生に対してきめ細やかに、そして対話を重視することによって、歯科医師を目指すプロセスに導くことを心がけております。臨床においては一度も同じケースはありません。知識偏重になってしまうと実際の患者を教科書の型にはめ込んでしまい、自分自身で考えることのできない歯科医師になってしまうことが危惧されます。学生個々の学力向上に向けた改善策は、結果のみではなく、その思考のプロセスを面談で聞くことにより能動的学習を促したいと考えております。基礎知識の中から、自分自身で論理的思考を育むことにより学生の学習意欲の向上を図るために、日頃からの学生とのコミュニケーションによってマイルストーンを設定し、達成型教育を推進したいと考えております。
最後に、先端歯科医学に対して敏感になれる歯科医師として大学院生の教育も実践しております。デジタル技術の発展によって歯科臨床の診療内容も変わりつつあります。歯科医師となって臨床現場で新しい技術や知識を理解して取り入れられるように、その先端材料や技術の研究や動向を学ぶことができる環境を整えていきたいと考えております。国内外問わず、論理的な思考を有し、行動できる大学院生の育成に注力したいと考えています。 学部学生であれば卒業時に自分で判断する力(問題解決能力)を有し、患者を思う人間性や倫理観を有する学生を、大学院生では修了時に、国際的にも教育的指導ができる歯学生の育成に努めたいと考えます。歯科理工学がすべての歯学生にとって将来の立派な歯科医師として常に先端的研究に注目し、実践的知識と併せていけることに役立つ教育を目指しております。
[研究面]
当分野の研究コンセプトは、臨床現場での疑問を解決するための研究を社会的背景に基づいて遂行することであります。臨床経験が豊富な教員が多いことから日常の臨床での疑問を解決するべく、歯科材料や機器に関する基礎研究を中心に行っております。
特に、CAD/CAM技術によるデジタルワークフローは確実に普及し、加工方法も切削加工(除去加工)法のみでなく積層造形法も可能になってきております。これらの加工方法の発展により、これまで使用できなかった材料や複雑な形状の補綴装置が製作できるようになり、歯冠修復物や補綴装置の製作過程は新たなフェーズに移行しております。使用できる材料の選択肢が増えることは患者に有益である一方で、製作方法の違いによってその材料特性である機械的性質や化学的性質は異なることが考えられることから基礎的知見を調査研究することが必要であります。デジタル化による歯科治療に関する研究の内容の調査・情報収集から基礎研究に着手し、新規歯科材料の開発や自らが考案した技術等を評価しております。そのデータをエビデンスとして、臨床に還元するトランスレーショナルリサーチを実践することで、今後も引き続き、患者のQOL向上に役立てる研究を遂行して、世界に発信していきたいと考えおります。
当分野ではCAD/CAM技術を応用した歯冠補綴装置の摩耗挙動に関する研究をはじめ、付加造形技術による歯冠補綴装置の開発・評価、新規コンポジットレジンの開発、β-TCPの新規合成法、ガラスセラミックスの結晶構造と性質の関連性の解明、高齢社会における義歯の新たな清掃方法の考案等の研究を進めております。